こんにちは、アラフォー太郎です。いつもお読みいただきありがとうございます!
今回は、老後2000万円問題に関する記事をお届けします。
今更ながら、このままの生活や貯金を続けるだけで、安定した老後を送れるのだろうか?こんな不安を感じました。
私同様「老後2000万円問題」という言葉を聞いて、漠然とした不安を感じている方は少なくないでしょう。
トヨタ自動車の社長からも「これまでのように終身雇用を継続することは難しい」というコメントが出ていますし、政府からも新NISAを活用した投資のススメがなされています。
事実、公的年金だけで悠々自適な老後の生活を支えてもらえる時代は終わったと思った方が良いでしょう。
そして今後、高齢化が益々進むことから、公的年金の家計への貢献度は現状より悪化すると想定するべきでしょう。
しかし、この問題は「解決できない」ものではなく、「知って、行動すれば乗り越えられる」ものです。
この記事では、老後2000万円問題の基本的な理解から、具体的な対策までを分かりやすく解説していきます。
漠然とした不安を解消し、安心して老後を迎えるためのロードマップを一緒に見ていきましょう。
この記事が、あなたが抱える老後への不安を払拭し、あなたが行動を開始するきっかけになることを祈って…。
1. 老後2000万円問題とは何か?
まず、この問題の根源を理解することからスタートしましょう。
2019年に金融庁の金融審議会が発表した報告書によって、夫婦二人の老後生活において、年金だけでは毎月約5万円が不足し、30年間で約2000万円が不足するという試算が示されました。
これが「老後2000万円問題」と呼ばれるようになった背景です。
重要なのは、この金額はあくまで「平均的な試算」であり、個々のライフスタイルや収入によって大きく変動するという点です。
しかし、この報告書は、公的年金制度だけに頼るのではなく、自助努力による資産形成の必要性を浮き彫りにしました。
「老後2000万円問題」の概要や対策をまとめて知りたいという方はこちらの書籍もオススメです。私はこの書籍で概要を知り、実際に行動を起こしました。
2. なぜ2000万円が必要と言われるのか?
では2000万円という数字は、具体的にどのように算出されたのでしょうか?
- 夫婦二人の平均的な生活費: 総務省の家計調査に基づき、夫婦二人の高齢無職世帯の生活費が月々約26万円。
- 公的年金の受給額: 厚生労働省のデータなどから、夫婦二人の標準的な年金受給額が月々約21万円。
- 毎月の不足額: 26万円 – 21万円 = 5万円の不足が発生します。
- 老後期間の積算: 65歳で引退し、95歳まで生きると仮定すると30年間。
- 総不足額: 5万円 × 12ヶ月 × 30年 = 1800万円。これに予期せぬ出費や医療費などを考慮し、約2000万円と試算されました。
もちろん、この数字はあくまで目安です。
持ち家の有無、健康状態(どれくらい長生きするか?長生きリスクというやつですね)、趣味や交際費にかける金額などによって、必要な金額は大きく変わってきます。
当たり前の話ですが、そもそもの支出が多くない人は不足額も少なくて済みますし、老後に優雅にお金を使って生活したいという方は不足額はその分増えます。
3. 不安を解消するためのロードマップ:具体的な対策
では、この漠然とした不安を解消するために、具体的にどのような行動を起こせば良いのでしょうか?
まずは、自分の現状を正確に把握することから始めましょう。
- 家計の収支を把握する: 毎月の収入と支出を詳細に把握し、無駄な出費がないか見直しましょう。家計簿アプリやエクセルを活用するのがおすすめです。
- 現在の貯蓄額を確認する: 銀行預金、証券口座など、現在保有している資産の総額を把握します。
- 理想の老後生活を具体的に描く: 老後にどんな暮らしがしたいのか、どれくらいの生活費が必要になりそうか、具体的に考えてみましょう。旅行に行きたい、趣味に没頭したいなど、具体的なイメージを持つことで、目標額も明確になります。
- 目標金額を設定する: 現状把握と理想の老後生活を基に、具体的にいくら貯める必要があるのかを算出します。
STEP1で家計の「見える化」ができたら、次は支出の見直しです。
- 固定費の削減: 住居費(住宅ローンの見直しや賃貸料の適正化)、通信費(格安SIMへの切り替え)、保険料(不要な保障がないか見直し)医療保険(高額で利回りの悪い積み立て保険)など、毎月必ず発生する固定費は、一度見直せば継続的で大きな節約効果があります。
- 変動費の削減: 食費、交通費、娯楽費など、日々の生活の中で見直せる部分がないかチェックしましょう。例えば、自炊の頻度を増やす、コンビニ利用を控えるなどが挙げられます。
- 無駄なサブスクリプションの解約: 利用していない動画配信サービスやアプリの月額課金など、見落としがちな支出を見直しましょう(私もいくつか動画配信サービスを解約しました)。
節約によって生まれた余剰資金を、ただ銀行預金に置いておくだけでは、物価上昇(インフレ)に負けてしまう可能性があります(現在の日本では特に意識すべきポイントです)。効率的に資産を増やすためには、資産形成を始めることが重要。
- 新NISAの活用: 少額から始められ、投資で得た利益が非課税になるお得な制度です。特に「つみたて投資」は、長期・積立・分散投資を後押しする制度であり、初心者の方におすすめです。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用: 自分で掛金を拠出し、運用する私的年金制度です。掛金が全額所得控除の対象となるため、節税効果も期待できます。原則60歳まで引き出せないというデメリットもありますが、老後資金専用の貯蓄としてならば活用できます(長期で資産形成する分には問題ありません)。
- 投資信託: 複数の株式や債券などに分散投資する金融商品で、専門家が運用してくれるため、初心者でも始めやすいのが特徴です(私は新NISAで投資信託に投資しています)。
- 株式投資・不動産投資: リスクは高まりますが、大きなリターンを期待できる可能性もあります。ただし、十分な知識と情報収集が必要です。
【重要】リスクとリターンのバランス
資産運用にはリスクが伴います。元本保証のない商品も多いため、自分のリスク許容度を理解し、無理のない範囲で始めることが大切です。分散投資を心がけ、一つの商品に集中投資しないようにしましょう。
資産形成だけでなく、長く働くことも老後資金の確保に貢献します。
- 定年延長・再雇用制度の活用: 企業によっては定年延長や再雇用制度を設けています。これらを活用することで、収入を確保しながら年金の受給開始を遅らせ、年金額を増やすことも可能です。但し、定年後、再雇用後の給与は大きく下がる企業も多いことから、試算する際にはよく調べるようにしましょう。
- スキルアップ・キャリアチェンジ: 老後も働けるように、若いうちからスキルアップを図ったり、新たな資格取得を目指したりするのも良いでしょう。特に若いうちにスキルを身につけると、そのスキルに複利が効き、生涯賃金の向上に資する場合もあり、自己投資が1番の投資とされることもあります。
- 副業・フリーランス: 定年後も自身の経験やスキルを活かして、副業やフリーランスとして働く選択肢もあります(私もアラフォーにして、Youtubeとブログを始めました。本業を引退後も続けようと思っています)。
自分一人で全てを解決しようとせず、必要に応じて専門家の力を借りることも重要です。またご自身でFPの知識を習得し、将来の金融プランを自分で把握することも有用です。
- ファイナンシャルプランナー(FP): 家計の見直しから資産運用の相談まで、幅広いライフプランニングの相談に乗ってくれます。但し、”無料FP相談”などにノープランで参加すると、FP相談という入り口から、ぼったくり金融商品を売り付けられる可能性もありますので、よく注意することが必要です。
- FP検定受験: 自分の将来のお金は、自分で把握してシミュレーションするのも有用です。自分のことを一番理解して、最も大切に考えるのはやはり自分です。FP3級に合格する知識があれば、ライフプランニングするという意味では十分。試しに一度テキストを読んでみることをオススメします(私も2ヶ月程勉強して、FP3級の資格を取得しました)。
まとめ:漠然とした不安を具体的な行動へ
老後2000万円問題は、聞くだけで不安になるかもしれませんが、決して解決できない問題ではありません。
- 現状を把握し、目標を設定する
- 支出を見直し、節約する
- 計画的に資産形成を始める
- 長く働く、働き方を見直す
- 必要に応じて専門家へ相談する、FPの知識を身につける
これらのステップを一つずつ着実に実行していくことで、漠然とした不安は具体的な行動へと変わり、安心して老後を迎えるための基盤を築くことができます。
今日からできることを見つけ、行動を始めてみましょう。未来のあなたが、今のあなたに感謝する日が来るはずです。
もし、この記事を読んで、具体的に家計を見直したい、資産形成について相談したいと感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。
あなたの老後への不安を解消し、豊かな未来を築くためのお手伝いをさせていただきます。
投資の始め方・書籍レビューも公開中ですので、以下の記事も合わせて参考にしてみてください。
投資を始めたきっかけとインデックス投資の魅力→
投資初心者におすすめのお金の名著も紹介しています。一緒に投資へのモチベーションもアップ!
気になる記事があれば、ぜひ読んでみてくださいね。
この記事が少しでも役に立ったら、SNSでシェアしていただけると嬉しいです!皆さまの“老後の不安が解消される”ことを祈って…。
もし「また読みたいな」と思っていただけたら、ぜひブログのフォローをお願いします。X(旧Twitter)でも更新のたびにポストしてますので、ポチッとフォローしていただけると泣いて喜びます!
他にも趣味に関する記事を書いておりますので、ご興味があればこちらも読んでみて下さい。共通の趣味をお持ちの方はご遠慮なくコメントで絡んでくださると泣いて喜びます。
お問い合わせ、コメントなどございましたらお気軽にお寄せいただけたら嬉しいです。
それでは。

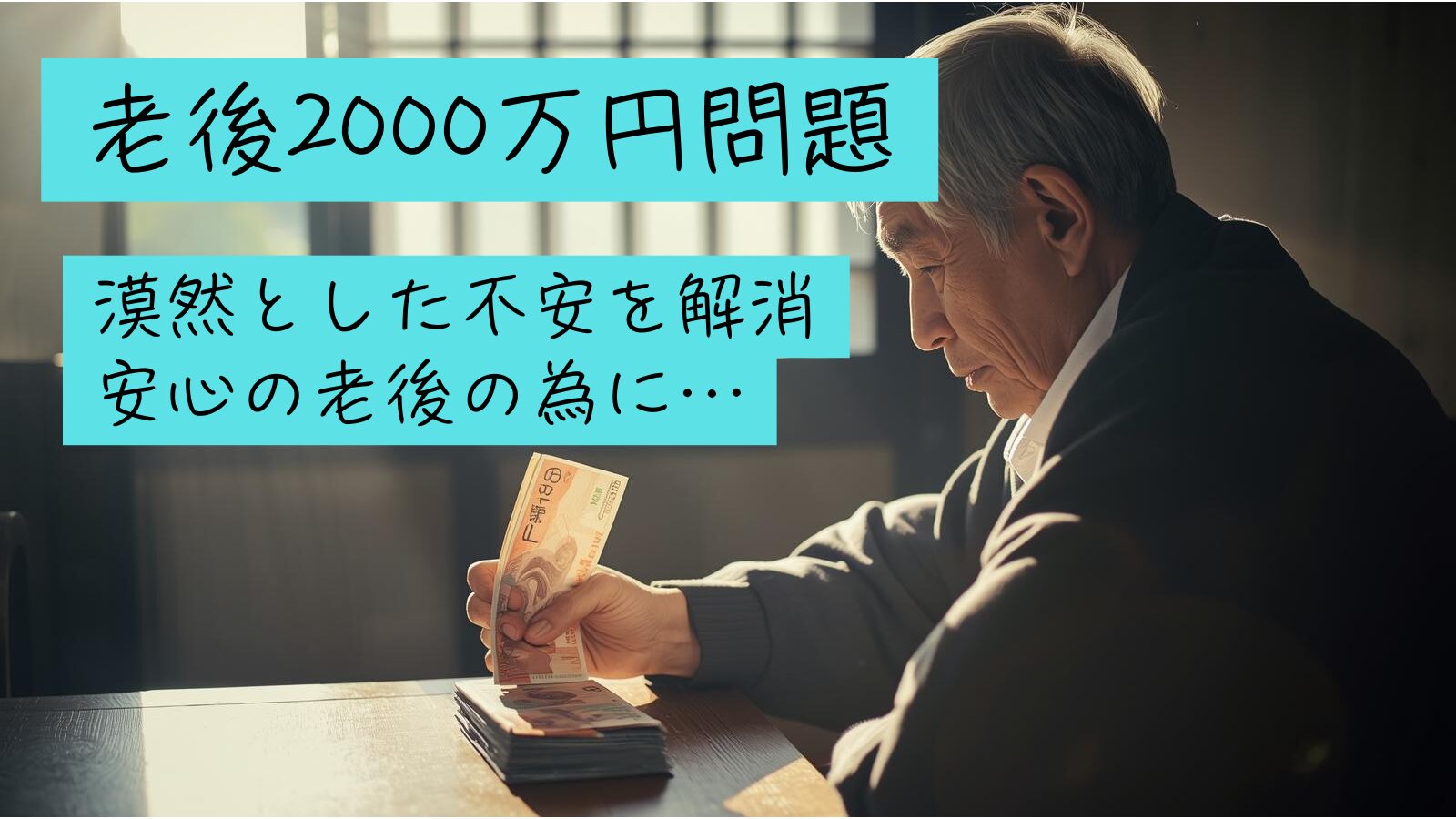


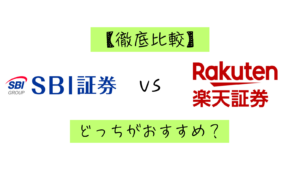
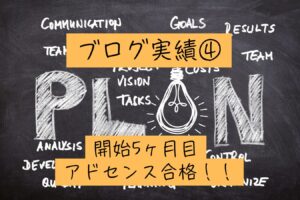




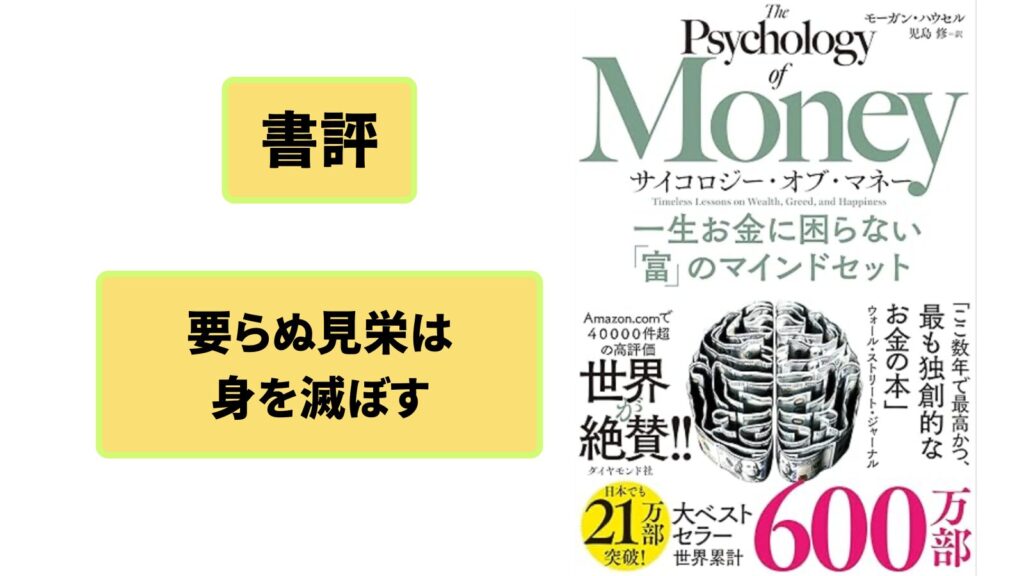
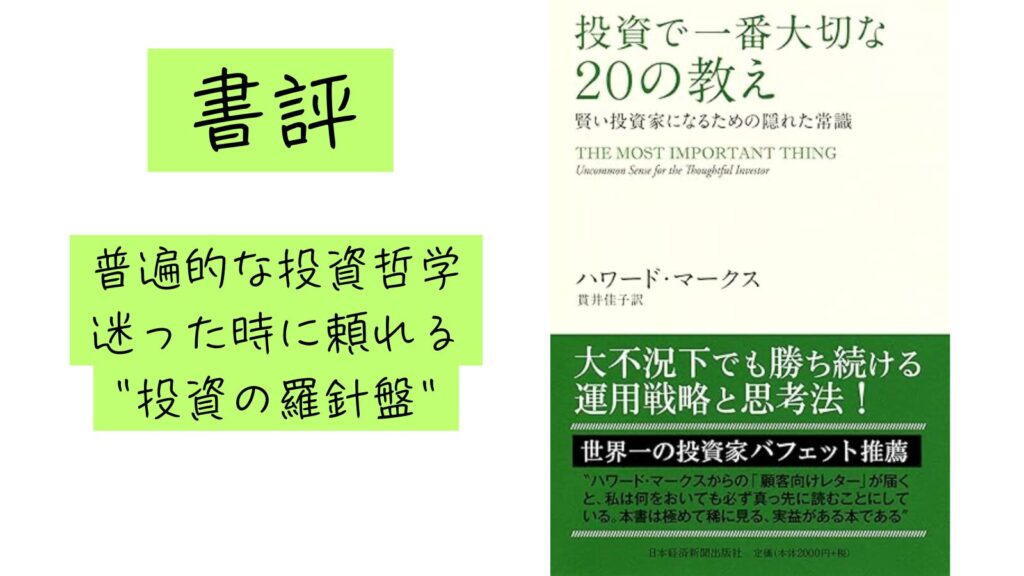
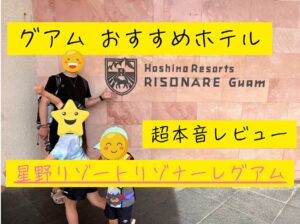
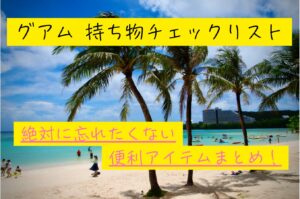




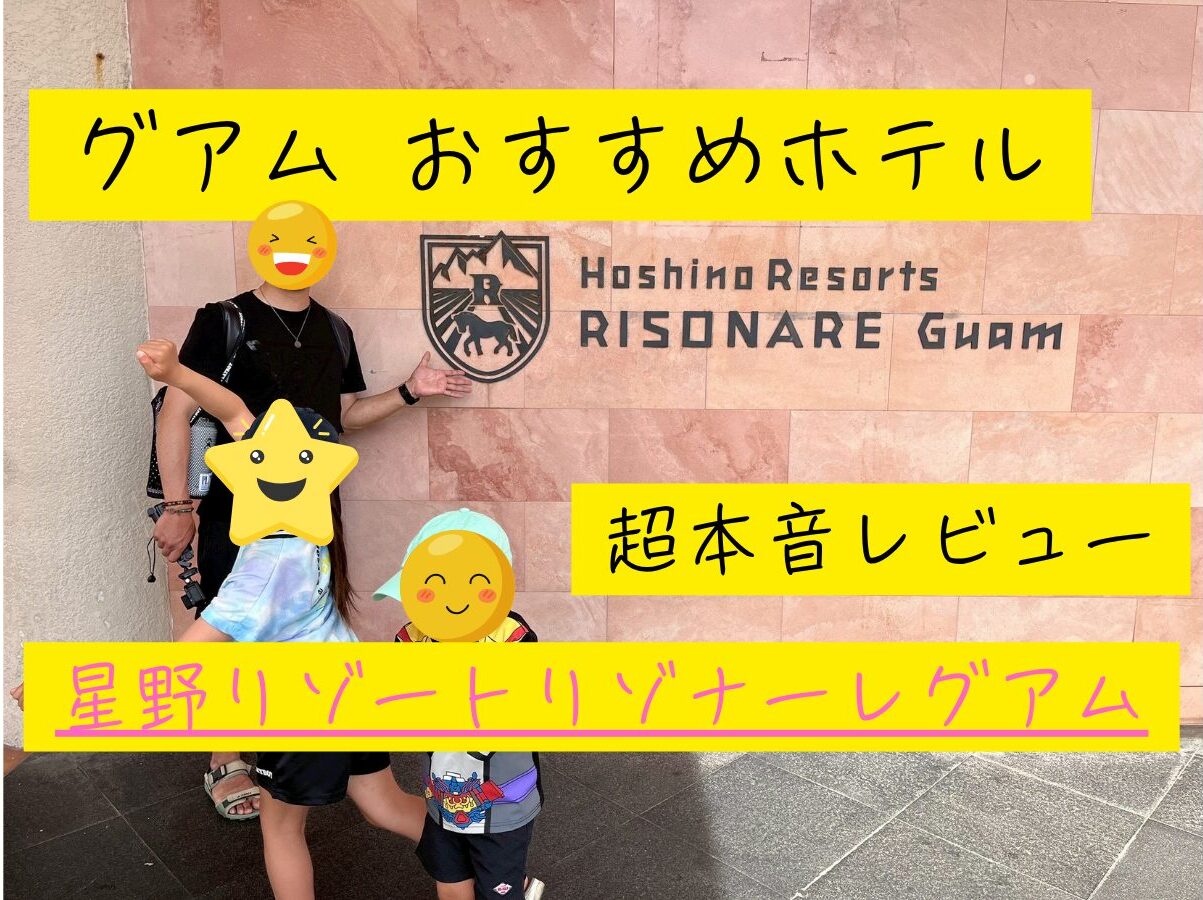


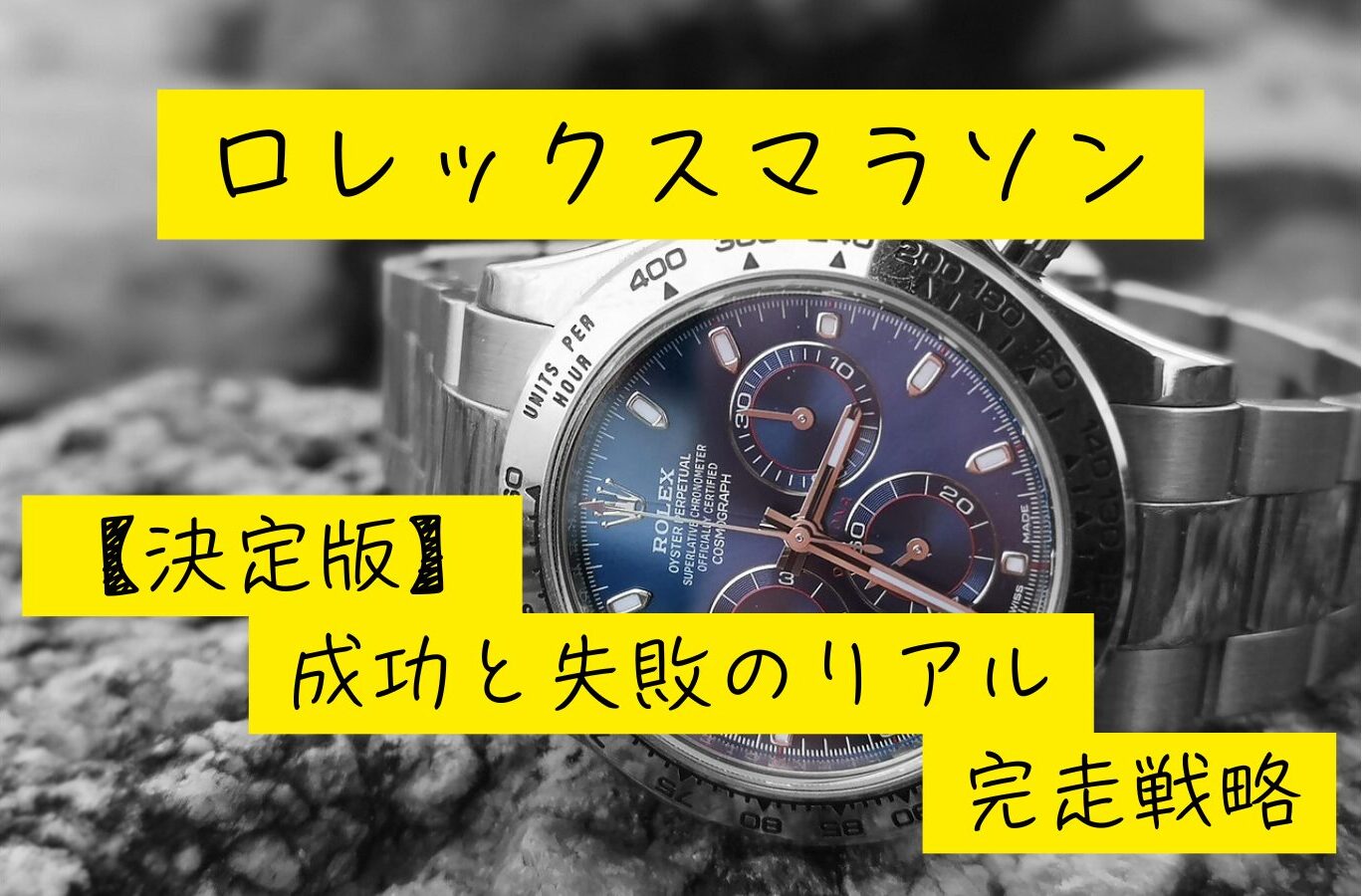






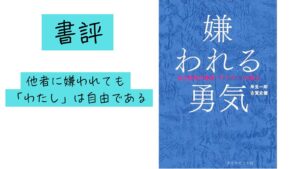

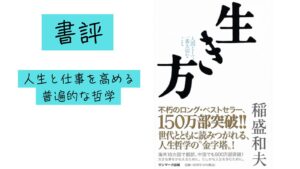
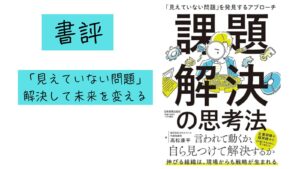
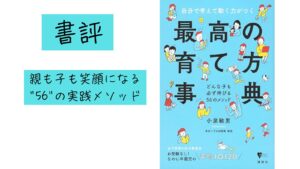
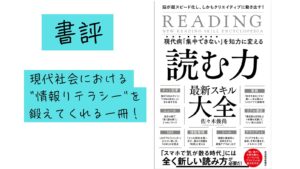

お問合せ・コメントはこちらから!